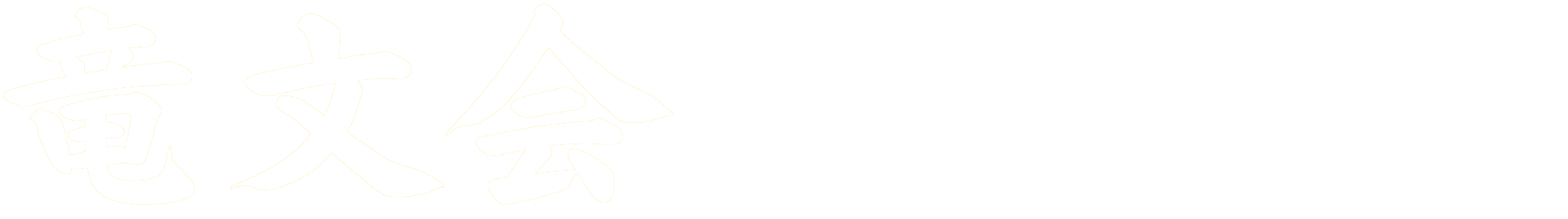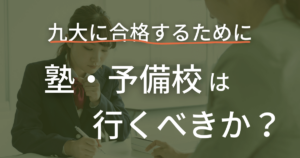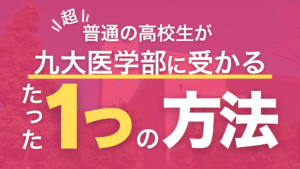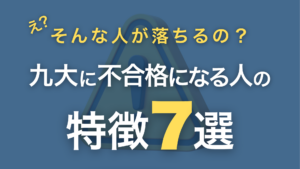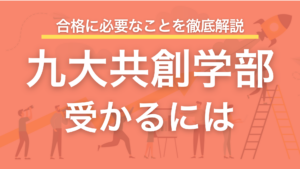九大工学部に受かるには?合格に必要なことを徹底解説!
この記事でわかること
- 何点取れば九大工学部に受かるのか?
- 九大工学部に合格するコツ
- 合格する人の考え方
「九大工学部に受りたい!」
あなたのこの悩みを120%解決する記事を作りました。この記事では、あなたが九大工学部に受かるために必要な情報を全て公開します。
ほんの一部だけ話しておくと・・・
- 何点取れば受かるのか?
- 九大工学部に合格するコツ
- 合格する人の考え方
ね、読みたくなったでしょ?大袈裟でもなんでもありません。九大工学部に受かるための情報を全て詰め込みました。
 中原先生
中原先生断言しますが、ここまで詳しい話はこのブログにしかありません。
誇張でもなんでもなく、この記事を読み終わる頃にはあなたは九大工学部に受かるための情報を全て手に入れることができる。そんな内容であると胸を張って断言します。
九大工学部の難易度を把握する
では早速本題に入っていきます。今回は、あなたが九大工学部に受かるために必要なことを順を追ってお話しします。
九大工学部の難しさ
最初に知って欲しいのは、九大工学部の難易度です。
『敵を倒すには、敵のことを知れ』
あなたは九大工学部がどのくらい難しいか知っていますか?
九大工学部の偏差値
| 工学部 | Ⅰ群 | 55 | 57.5 | 63 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ群 | 53 | 55.0 | 63 | |
| Ⅲ群 | 55 | 57.5 | 63 | |
| Ⅳ群 | 53 | 55.0 | 62 | |
| Ⅴ群 | 55 | 57.5 | 63 | |
| Ⅵ群 | 53 | 57.5 | 63 |
- 駿台の偏差値は「高3第1回駿台全国模試」のA判定
- 河合の偏差値は河合塾が公表する合格可能性50%の『ボーダー偏差値』
偏差値を見てどのように感じますか?「予想外に低いな」と思いませんでしたか?
無理はありません。だって、偏差値57.5とかって低そうじゃないですか?
こうやって油断することで九大に落ちる人が続出します。いや、勉強しなさすぎて受験すら諦めることになるかもしれません。
覚えていて欲しいのですが、偏差値を知ることに意味はありません。だって、あなたが受ける模試によって九大工学部の偏差値は違うから。
当然ですが、受験者のレベルが高い模試を受けた偏差値は低くなる。一方、受験者のレベルが低い模試を受けたら偏差値は高くなります。
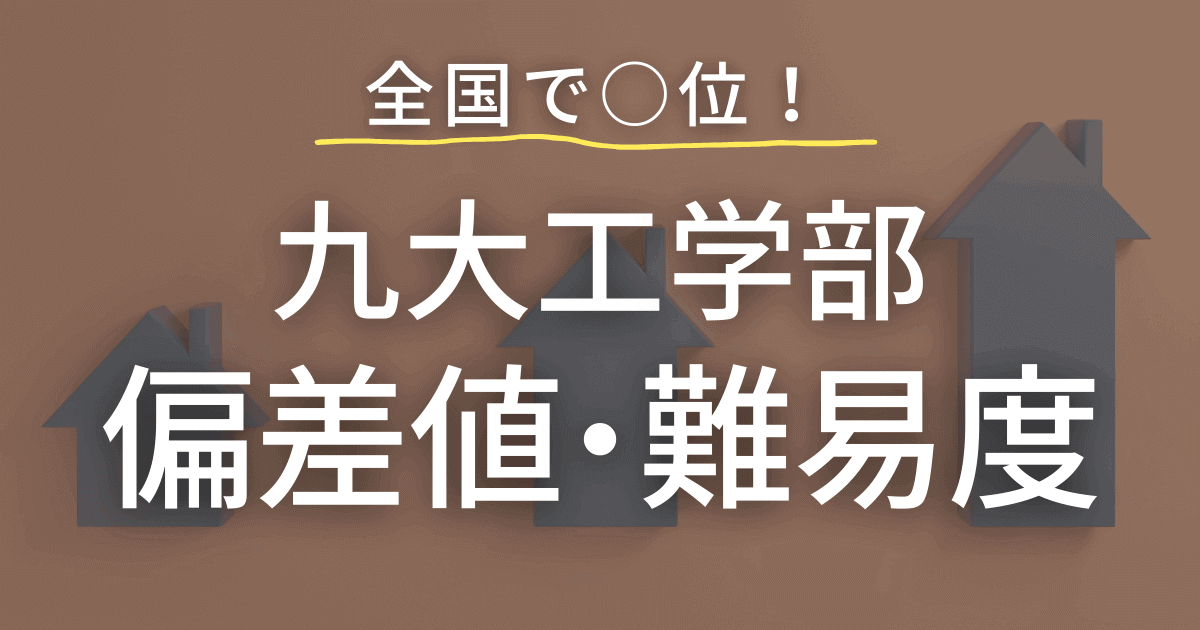
自分のレベルを把握する
だからこそあなたは自分で受けた模試を基準にするべきです。模試を受けるとB判定とかD判定といった志望校の判定が出ますよね。あなたの九大工学部の判定はどうなっていますか?
A判定でしょうか?A判定ならちょっとは油断してもいいかもしれません。でもそれ以外の判定なら気を引き締めるべき。絶対に合格できるレベルとは程遠いということです。
ちなみに、進研模試を参考にするのはおすすめしません。おすすめの模試は、以下の2つ。
- 全統記述模試
- 駿台全国模試(高2まで)
九大工学部はかなり難易度が高い。模試も難しめの模試を参考にするべき。おすすめは全統記述模試。
「全統記述模試を受けたことない・・・」という場合はヤバい。次回からは必ず受けるようにしましょう。
ちなみに校内順位もおすすめです。特に実力テストでは参考になります。九大に現役で50人合格する高校なら、単純に考えて50番以内に入ればOK!
九大工学部は九大の中では難しい学部である。また、余裕を持って合格したいので25〜30番以内を狙うのが無難です。
過去問を解くのが一番おすすめ
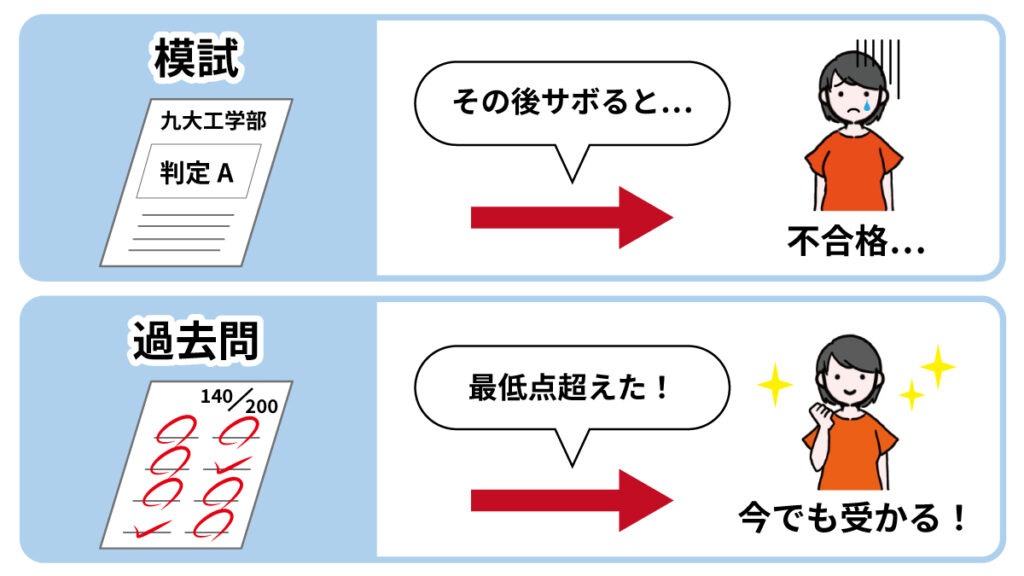
ちなみに、一番おすすめなのは過去問を解くこと。模試の判定はあくまで現時点での相対評価。つまり、今の段階では受かるレベルにいるよって意味。仮にA判定だとしても、今から勉強をサボれば当然ですが不合格になります。
一方、過去問を解いて合格最低点を超えることができたらどうでしょうか?少なくとも九大に合格できる最低ラインの実力はあるということ。
たまにね、「模試でA判定だから!」と油断する九大受験生がいます。そして、こういう生徒ほどどんどん成績が下がり不合格になる。
もちろんね、A判定を取ることはすごいこと。合格者でもA判定で合格できる人は少ない。本当に素晴らしいことです。でもね、A判定が取れても油断したら意味がない。これまでの努力が水の泡です。
こんな悲しいことが起こらないためにも合格最低点を指標にするのがおすすめ。合格最低点を取れていれば、今の時点でも九大工学部に受かるということ。(本来ならダメですが)ちょっと油断しても何とかなります。
ということで、今すぐに過去問を解きましょう。そして、あなたと九大工学部の距離を把握しましょう。
「過去問が全然解けない」というのであれば、死ぬ気で努力しないといけないということです。
九大工学部に受かるマインド
では続いて、九大工学部に受かるためのマインドをお話しします。気持ちの持ち方はめちゃくちゃ大事。
意外と知られていませんが、気持ちの持ち方次第で九大工学部の合否は変わる。これは事実です。
勉強に取り組む前に九大工学部に受かるためのマインドをあなたの中に取り入れましょう。これだけでも合格可能性は2倍、いや3倍に跳ね上がる可能性があります。
競争に勝て
一番大事な考え方は、『何とかして競争に勝て』ということ。
「そんなこと言われてなくても分かってる」と思われるかもしれません。でもね、本当の意味で理解している人は少ない。
九大受験に限らず大学受験は相対評価です。つまり、ライバルより1点、いや0.1点でも高い点数を取ることが出来たら合格できます。
では、ライバルより高い点数を取るためには何をしたらいいのか?絶対にすべきことは、ライバルよりもたくさん勉強すること。『競争に勝つ』という大前提にあるのは、周りの友人より1分でも多く勉強しろということ。
このことをあなたは理解できていますか?「今日は2時間勉強したからいいや」と妥協していませんか?ライバルが3時間勉強してたら差をつけられているだけ。勉強しているのに成績が下がっているという悲しい状況です。(あなたは気がついていないですが・・・)
時間は全く残されてない
次に知って欲しいのは、『時間は全く残されていない』ということ。九大工学部に落ちる生徒のほとんどはこれが原因。
「まだ受験は先だから大丈夫!」
「今のうちはこのくらい勉強しておけばいい」
と楽観視しすぎ。
本当なら時間が全然足りないのに悠長に勉強してるから落ちるわけです。考えて欲しいのですが、合格したいのは九州大学ですよね。選ばれた生徒が通う進学校でも、九大に現役合格するのは10〜30%程度。そんなレベルの九大に悠長な勉強をして受かるはずがありません。
でもね、なぜか楽観的に考えるんですよね。もしかして高校受験を基準に考えていませんか?「高校受験は中3の夏休みから勉強を始めて間に合ったから、大学受験も大丈夫」こんな感じで考えていると取り返しがつかなくなります。
九大受験は高校受験の10倍、いや20倍は大変。理系数学を仕上げるだけでも、高校受験の5倍は大変です。これを心に刻み込んでください。
あなたに時間的余裕はありません。今から全ての勉強時間を捧げてギリギリ。もしかしたら間に合わないかもしれません。
九大工学部合格に必要な情報を集める
これまでの話で九大工学部を目指すにあたり、大事な考え方を持つことが出来ました。きっと、「全力で頑張る!」とやる気にも満ちているはず。では、ここからが本格的に勉強の話です。
まずは必要な情報を集めましょう。必要な情報としては、
- 入試科目
- 各科目の傾向や頻出単元
- 合格最低点
この3つは最低でも押さえておきたいところ。というか、知っておかないと話になりません。知っているかどうかで、勉強効率が格段に変わってきます。
各科目の傾向や頻出単元は分かりやすいと思います。『九大で出やすい問題』を知っているどうかで、合格最低点を超える難易度は格段に下がる。要は合格しやすくなります。
調べないで勉強を始めるのは自殺行為。必ず自分なりに調べてから勉強に取り組みましょう。
九大工学部の入試科目
まずは入試科目から。
九大工学部の入試科目はこんな感じ。
九大工学部 入試科目
| 共通テスト | 国語(現代文+古典) 数学(ⅠA・ⅡBC) 英語(リーディング・リスニング) 理科(物理・化学必須) 社会(地総・地理探求、歴総・日本史探求、歴総・世界史探求、公共・倫理、公共・政治経済より1科目) 情報 |
|---|---|
| 2次試験 | 数学(ⅠA・ⅡB・ⅢC) 英語 理科(物理・化学必須) |
とはいっても、入試科目はそこまで気にしなくていいです。九大工学部は物理と化学が必須。生物と地学では受けられないことを知っておくだけでOK!
一方、配点は意識しておく必要があります。
九大工学部 配点
| 共通テスト | 2次試験 | 合計 |
|---|---|---|
| 525点 情報のみ75点に圧縮 | 700点 | 1225点 |
| 2次試験の内訳 | ||
| 数学 | 英語 | 理科 |
| 250点 | 200点 | 250点 |
大事なポイントは2つ。1つ目は、共通テストの情報の配点が大きいこと。他の科目は50%に圧縮されますが、情報は75%と配点が大きい。「情報はあとでいいや」と油断する人がいますが、九大工学部を狙うなら対策が必須です。
2つ目は2次試験の理科の配点が大きいこと。数学と同じ配点で英語より大きい。「数学と英語がとりあえず大事」と思っている人がいますが、九大入試では理科も大事。このことを知らないで勉強に挑むと痛い目を見ます。
「高3の夏までは数学と英語に力を入れる」という受験生がいますが、これでは間に合わない。理科が間に合わなくて不合格・・・の悲しい未来が待っています。理科は数学と同じくらい大事だと意識して早めに勉強に取り掛かりましょう。
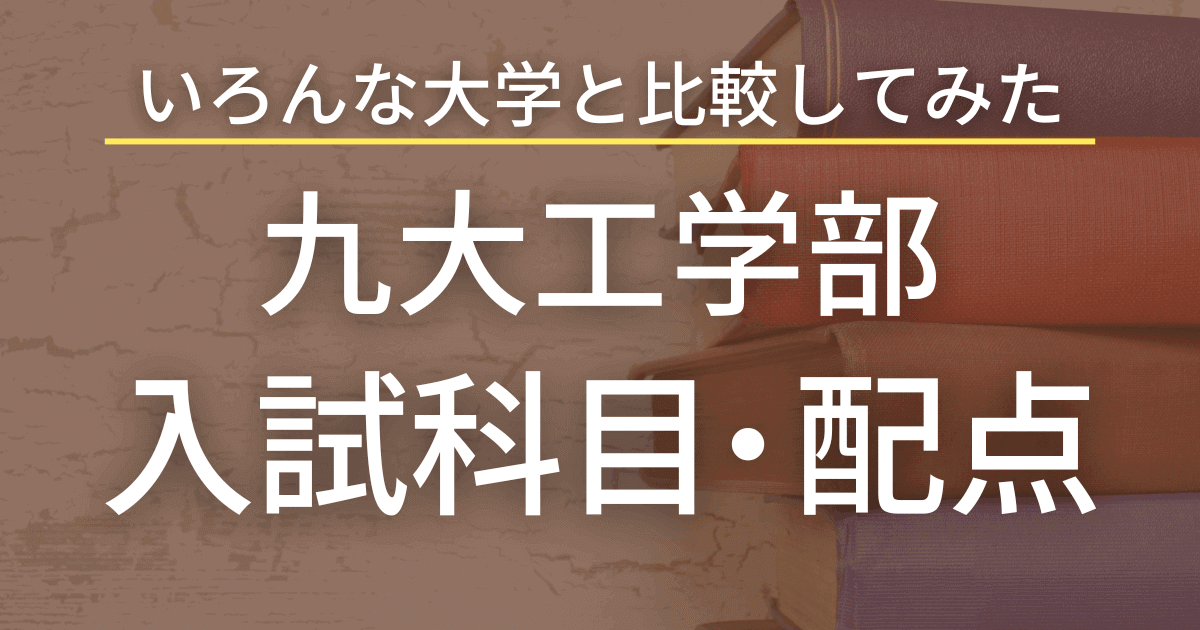
各単元の傾向や頻出単元
九大工学部を本気で狙うなら各科目の傾向や頻出単元を把握することも大事。「確率が頻出」と分かったら、確率を重点的に勉強すべきじゃないですか?だって、よく出る単元を勉強した方が効率がいいですよね。
ということで、勉強を始める前に各科目の特徴についてリサーチすべき。特に2次試験は絶対にやっておきましょう。ちなみに、一番手っ取り早いことは過去問を解くことです。
ここでは簡単に九大工学部の各科目の傾向や頻出単元をまとめておきます。もっと詳しく知りたい場合は、各科目の分析記事をご覧ください。科目名をクリックしたら各科目ごとの分析記事を見ることが出来ます。
九大工学部 各科目の傾向・頻出単元
| 理系数学 | 難易度は標準〜やや難。難易度の変化が激しいのが特徴。 完成までに一番時間がかかる科目。 ⅢCが合格の生命線。頻出単元としては、整数・確率・ベクトル・複素数平面・微積。 標準的な年であれば5割を目標に勉強したい。 |
|---|---|
| 英語 | 難易度は標準的。九大の2次試験で点数を取るのが一番簡単な科目。 問題構成は長文読解(3題)+自由英作文(2題)。 長文読解を仕上げるのは当然としては、自由英作文もしっかり対策が必要。 目標得点は6割。 九大工学部に受かりたければ、理系であろうと英語も得点しなくてはならない。 |
| 物理 | 難易度は標準。ただ、物理という科目の特性まで考慮すると、受験生にとっての体感はやや難。 高得点が取りやすい試験。 問題構成は、力学+電磁気+波動or熱力学。 高校で最後で学習する電磁気の完成度が大事。 目標得点は7割。工学部を目指すならこのくらい取らないと話にならない。 |
| 化学 | 難易度は標準。 大問数が多く、知識問題もあるので安定して高得点が取れる試験。 問題構成は、理論化学(2題)+理論・無機化学+有機化学+高分子化合物。 九大化学は理論化学の完成度次第。 目標得点は7割。 九大工学部に受かるための生命線は理科である。 |
九大工学部の合格最低点
最後に調べて欲しい情報は合格最低点。理想は、過去問を解いて自分の点数と合格最低点を比較すること。これで、今のあなたと九大工学部の距離が明確になります。
というか、合格最低点を知らないと話になりません。各科目をどのくらい勉強すればいいかという学習計画を立てることが出来ないので。合格最低点だけは絶対に把握しておきましょう。
九大工学部 合格最低点
| 学部・学科 | 年度 | 合格最低点 (得点率) |
|---|---|---|
| 工-Ⅰ群 | 2024年 | 736.0(64.0%) |
| 2023年 | 723.5(62.9%) | |
| 2022年 | 684.5(59.5%) | |
| 工-Ⅱ群 | 2024年 | 701.0(61.0%) |
| 2023年 | 677.0(58.9%) | |
| 2022年 | 645.0(56.1%) | |
| 工-Ⅲ群 | 2024年 | 729.5(63.4%) |
| 2023年 | 684.0(59.5%) | |
| 2022年 | 651.5(56.7%) | |
| 工-Ⅳ群 | 2024年 | 697.5(60.7%) |
| 2023年 | 668(58.1%) | |
| 2022年 | 639.5(55.6%) | |
| 工-Ⅴ群 | 2024年 | 715.5(62.2%) |
| 2023年 | 679.0(59.0%) | |
| 2022年 | 675.5(58.7%) | |
| 工-Ⅵ群 | 2024年 | 701.5(61.0%) |
| 2023年 | 680.0(59.1%) | |
| 2022年 | 642.5(55.9%) |
※ 情報抜きの1150点満点
あなたが目指す学科の合格最低点は最低でも3年分は把握しておきましょう。
九大工学部に受かるための得点戦略
必要な情報を集め終わりました。次にして欲しいのは『得点戦略』を考えること。
得点戦略とは、あなたが九大工学部に受かるための点数の取り方。各科目で何点ずつ取るかを具体的に考えていきましょう。
とはいっても、自分で考えるのは難しいでしょう。何となくでも大丈夫。勉強に具体性を与えるのが目的なので、「とりあえず」で構いません。
『得点戦略』を決めるさいのポイントは2つ。
- 合格最低点を目標にしない
- 過去問を解いた結果を参考にする
1つ目のポイントは、合格最低点を目標にしないこと。合格最低点を知っておくべき、と言いましたが、合格最低点を目指していては合格なんて出来ません。
理想は、合格者最低点+30〜40点を目指すこと。工学部I群なら、770点くらいを目指すといいでしょう。(情報抜きの1150点満点)
2つ目のポイントは、過去問を解いた結果を参考にすること。得意科目や苦手科目がありますし、受験生1人1人で勉強の進捗は全然違う。当然ですが、目標にすべき点数も変わってきます。
そこで、過去問を解いて合格戦略に反映するのがおすすめ。とは言っても、そこまで難しく考える必要はありません。過去問を解いてみて「英語は難しいけど、数学は頑張ればいけそう」と思うなら、英語の目標点を下げて数学を上げる。こんなイメージです。
試しに作ってみましょう。目標点は、770点。(情報抜きの1150点満点)共通テストはわかりやすく、ボーダーの78%(351点)とします。2次試験で必要な点数は約420点になります。これを数学・英語・理科でどのように確保するか考えましょう。
過去問を解いてみたら、「数学・物理は取れるけど、化学が微妙」だったとします。
| 数学 | 英語 | 物理 | 化学 |
|---|---|---|---|
| 135点(54%) | 120点(60%) | 90点(72%) | 75点(60%) |
ざっくり、こんな感じでしょうか?何度も言いますが、厳密に考える必要はありません。
作る理由は今後の勉強の指標にするため。勉強が進むにつれて目標点は変わってきます。つまり、どんどんアップデートするから今考え込みすぎるのは時間の無駄です。
ちなみに、現実的に考える必要はありません。欲張って全然OK!「まあ、勉強したらこのくらいは取れるでしょ」と楽観的に考えて大丈夫。だって、その点数が取れるように必死に頑張ったらいいだけですから。
『合格戦略』を作ることは大事。というのも、勉強に具体性を持たせることができる。目標点が決まればすべきことも見えてきます。
九大工学部に受かるための勉強内容
『得点戦略』を作れば、九大工学部合格への準備はかなり整いました。次にやって欲しいのは、各科目の具体的な勉強計画を立てることです。
先ほど考えた目標点を取るために具体的に何をすべきか。これを考えていきましょう。
細かく考えすぎると時間が足りないので、以下の3つを意識してください。
- どの問題集を使うか
- いつまでに終わらせるか
- 過去問はいつから解くか
ここでは、2次試験に必要な科目についてお話しします。今から話すのはあくまで一例なので、あなたの状況に応じて作り替えてください。
数学
数学でおすすめの教材は青チャート。なので、青チャートをメインに考えていきます。
なお、九大合格に向けた各科目の勉強法やおすすめの参考書は別の記事で詳しく紹介しています。各科目の最後にリンクを貼っておくので、必要な場合はそちらをご覧ください。
仮に高1の10月から勉強を始めるとして
青チャートⅠA(高2の5月まで)
⬇︎
青チャートⅡB(高2の12月まで)
⬇︎
青チャートⅢC(高3の7月まで)
⬇︎
理系数学の良問プラチカⅠAⅡB
スタンダード演習ⅢC(高3の11月まで)
⬇︎
共通テスト演習(高3の1月まで)
⬇︎
九大の過去問
あなたがすべきだと思った教材を書き出し、いつまでに終わらせるか考える。これで簡易的ではありますが、学習計画を作ることが出来ます。
簡易的ですが、作るのはめちゃくちゃ大事。というのも、期限を決めることで「5月までに終わらせないと!」というモチベーションに繋がります。人間は期限を決めてこそ本領を発揮する生き物。何をすべきか、だけでなく、いつまでに終わらせるかと絶対に決めましょう。
英語
英語はやるべきことが多く複雑です。ここでは、長文読解に向けた勉強計画だけを考えることにします。
仮に高1の10月から勉強を始めるとして
システム英単語(高2の12月まで)
Vintage(高2の5月まで)
⬇︎
入門英文解釈の技術70(高2の9月まで)
⬇︎
基礎英文解釈の技術100(高2の3月まで)
⬇︎
長文の問題集(1.5ヶ月に1冊)
⬇︎
(高2の11月から)
共通テスト演習
⬇︎
九大の過去問
何度も言いますが、あくまで一例です。この通りに勉強しても合格するかはあなた次第。自分の状況を加味して、あなた自身の学習計画を作ってください。
物理
次は物理。九大工学部に合格するための生命線は理科。なので、物理は確実に高得点を取る必要があります。85点(125点満点)が1つの基準になります。
仮に高2の10月から勉強を始めるとして
良問の風(高3の6月まで)
⬇︎
名問の森(高3の11月まで)
⬇︎
共通テスト演習(高3の1月まで)
⬇︎
名問の森の続き・九大の過去問
※ セミナーやリードαなど学校指定教材は意図的に外しています。状況次第では、これらに取り組む方がおすすめです。
化学
最後は化学です。九大工学部に合格するためには化学もかなり大事。九大の化学は高得点で安定しやすいので、確実に高得点を取りましょう。
仮に高2の10月から勉強を始めるとして
重要問題集A問題(高3の7月まで)
⬇︎
重要問題集B問題(高3の11月まで)
⬇︎
共通テスト演習(高3の1月まで)
⬇︎
重要問題集の続き・九大の過去問
※ セミナーやリードαなど学校指定教材は意図的に外しています。状況次第では、これらに取り組む方がおすすめです。
九大工学部に受かるために大事なこと
『得点戦略』を考え、勉強計画を作成しました。いよいよ勉強に取り組む段階です。
正直言って、ここまで真摯に取り組むだけでもかなりすごいこと。大体の九大受験生は途中で面倒くさくなって諦めます笑 ここまで仕上げただけで誇っていいでしょう。
ただ、勉強に取り組む段階でも失敗することはあります。ここまで付き合ってくれたあなたには失敗して欲しくない。ということで、勉強に取り組む前に大事なことをお話しします。
死ぬ気で勉強する
当たり前ですが、あえて言わせてください。一番大事なことは、死ぬ気で勉強すること。
せっかく得点戦略や学習計画を作っても勉強しなかったら意味はない。まさしく『絵に描いた餅』になるでしょう。
いいですか、あなたが目指している九大工学部はかなりハイレベル。九大の中でも難しい学部になります。当然ですが、並大抵の努力では入れない。死ぬ気で努力する必要があります。
万が一にも油断しそうになったら、難易度を常に思い出しましょう。分かりやすいのは定期的に模試を受けたり過去問を解くこと。模試でC判定やD判定だったり、過去問で点数が取れないなら油断すべきでない。
『入試当日まで油断せずに全力疾走する』
これがあなたが九大工学部に受かるための至上命題です。
勉強計画を常に見直す
勉強計画も常に見直すことを心がけましょう。残念なことに、あなたが最初に立てた計画の完成度は20%程度。いや、20%だったらいい方かもしれません。
勉強の進捗に応じて常にアップデートすることが必要です。入試本番までに少しずつ改良を重ねて100%を目指すイメージを持ってください。
勉強を進めるといろんな問題にぶつかります。
- 難しくて問題集が解けない
- 問題を解くのに時間がかかる
- 問題集は終わったけど解けるようにならない
こういう時は計画を見直す必要があるでしょう。
ちなみにうまくいっている時も計画の見直しは必要です。考えてみて欲しいのですが、英語が早く完成したらどうですか?かなり気持ちに余裕が出てきますよね?
つまり、勉強がスムーズに進む科目のペースを上げるのも大事なこと。他の科目に回す時間が多くなるので、苦手科目の点数アップにも繋がります。上手くいっている科目の計画も積極的に見直しましょう。
九大工学部に受かるためのコツ
では、いよいよ本格的に勉強を始める時です。
考え方はシンプル。
- ひたすら勉強する
- 定期的に学習計画を見直す。
これだけ。とはいえ、勉強する際のコツもいくつかありますのでお話ししておきます。
お話しするコツは5つ。
- 情報を疎かにしない
- 数学にこだわらない
- 理科が生命線
- 復習をしろ
- 英単語帳をこなせ

情報を疎かにしない
最初に大事なことは、情報を疎かにしないこと。九大工学部の情報の配点は75点。かなり大きいです。
もちろんね、数学や英語、理科を頑張ることは大事。2次試験で出題され配点も大きいので頑張らないわけにはいきません。
でも、数学や英語、理科で得点するのはなかなか大変。だったら情報で点数を取ったほうがよくないですか?
どの科目で点数を取ろうが同じ1点。だったら、取るのが簡単な科目で取るべきです。共通テストの情報はかなり楽。参考書も地理と比べて厚さが半分以下。つまり、少ない暗記量でコスパよく点数が取れるということです。
数学にこだわらない
数学にこだわらないのも大事なこと。数学って大事な科目な気がしますよね?確かに、九大工学部に受かるのに数学が大事なのは間違ってはいません。
ただ、数学を過大評価しすぎる人が多すぎます。それこそ、「1日の勉強時間のほとんどが数学」なんて人も珍しくありません。
でも、他の科目の勉強はどうするんですか?確かに数学は大事な科目です。ただ、九大工学部の配点1125点中、数学の占める割合は350点。確かに大きいですが、他の科目の配点の方がはるかに大きい。
それなのに、数学だけ勉強してるって時間の使い方が下手すぎませんか?
もちろんね、数学に時間をかける生徒の気持ちも分かります。高校数学って難しいし、1問を解くのにも時間がかかる。挙げ句の果てには、高校の先生が「とりあえず数学が大事!」と何回も言ってくる。
でも、九大工学部に受かるためには英語や理科も同じくらい大事。これを意識せずに勉強すると、勉強バランスで必ず失敗します。
理科が生命線
九大工学部合格には数学と同じくらい理科が大事。いや、理科の方が大事と言っても過言ではないかもしれません。実際、私は理科こそが『九大工学部合格の生命線』だと考えています。
この記事の中でも話しましたが、数学と理科の配点は同じ。ということは、少なくとも数学と理科は同じくらい重要ということです。
しかも、九大の理科は数学よりも点数が圧倒的に取りやすい。(年にもよりますが、)7割を取る難易度は、数学が理科の3倍。つまり、理科の方が3倍は点数が取りやすいということ。
どの科目で1点とっても1点は1点。だったら点数が取りやすい科目で取るべきですよね?
でも、みんな理科を舐めているんですよ。勉強を始めるのが遅い。
しかも、学校の先生で物理や化学は分かりにくい人が多いらしく、理解していない人も多い。こんな状況で九大入試で点数が取れるはずがありません。
九大工学部に受かりたいならもっと理科の重要性を認識しましょう。
復習をしろ
勉強で一番伝えたいことがこれ!絶対に復習するようにしましょう。
私も中学時代は復習を舐めてました。復習なんて全くせず、復習不足がたたって附設にはボコボコにされて不合格。高校から真面目に復習するようになります。
復習はね、絶対した方がいいです。成績の上がり方が全然違う。私の持論ですが、『復習をしないくらいなら勉強しない方がいい』といつも言っています。それほど復習は大事。
英単語帳をこなせ
勉強のコツの最後は、英単語帳に取り組むべきということ。「何を当然のこと言ってるの?」って気がしますよね。でも、大事なことなので言わせてください。
長文を読む上で英単語は大事。これはわかってますよね。
ただ、指導者の中には「英単語は覚えてなくていい。推測しろ」という人がいます。こんな嘘を教えるなんて、パフォーマンス以外ならヤバい。だって、暗記したら解決することをわざわざ頭を使って考えるんですよ。どう考えてもバカなやり方じゃないですか?
ここからが大事。『暗記したら解決する』がポイント。いいですか、暗記したら済むことはサボってはだめ。だって、必要なのはあなたの努力だけ。時間を確保して勉強すれば済む話。
英単語の暗記をサボる人がいますが論外。隙間時間を活用して暗記するだけで成績が上がるわけですから、やらない理由はありません。
九大工学部に受かる最強の考え方
いよいよ最後です。最後に九大工学部に受かる最強の考え方をお伝えします。この考え方ができるだけで合格可能性が2倍になることを約束しましょう。
まずは模試の判定を気にしないこと。もちろん「E判定でも頑張れば大丈夫」なんて悪い意味でポジティブなことを言っているわけではありません。
B判定でもC判定でも油断するなということ。たとえA判定だとしても同じです。
あなたが120%確実な合格を掴み取りたいなら、『合格最低点を超えるかどうか』これだけを指標にしてください。
あなたが油断していいのは、過去問を解いて合格最低点を超えたときだけ。これ以外は油断するなんて論外。ちなみに油断していいのも束の間だけ。
すぐに合格者平均点を目指して勉強再開です。これが最強の考え方。「模試でB判定だったから」なんて考えていると足元をすくわれますよ。
九大工学部の合格体験記
まさか九大工学部に受かるなんて
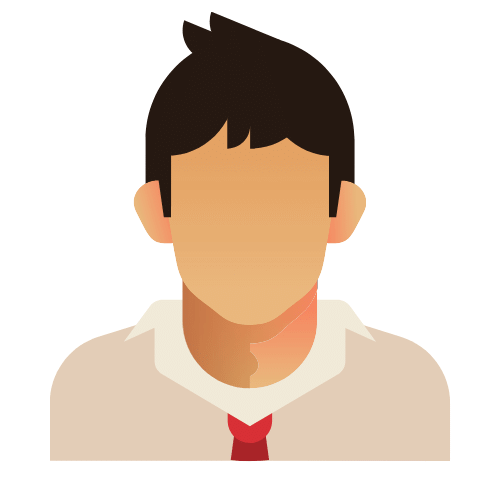
T・Kくん(オンライン受講)
九州大学工学部
現役合格
理科が急にできるようになりました!
- 入塾したのはいつですか?
-
高2の11月です。
- 入塾のきっかけはなんですか?
-
理科が絶望的に出来なかったことです。僕は数学が大事だと思い込んで、数学ばかり勉強してました。中原先生のブログを読んで、やばい理科をやらないといけないと焦り竜文会にすぐに問い合わせをしました。
- 合格した時はどうだった?
-
泣きそうになるくらい嬉しかったです。入会する前の成績はD判定やE判定ばかり。そんな僕が九大に受かるなんて信じられませんでした。
- 竜文会の通ってみてどうですか?
-
理科が一気にできるようになりました。特に化学が苦手だったのですが、中原先生に習ってみて理論化学が急にできるようになりました。高3の最初の全統記述模試では一番時間を割いてきた数学より化学の方が偏差値が高かったですww
- 最後に一言!
-
九大に合格するには理科が絶対必要です。理科を勉強して受かった僕が言うので間違いありません。
九大工学部に受かるにはのまとめ
今回の記事では『九大工学部に受かるには』をテーマに大事なことを話してきました。
いかがでしたか?
大事なことを簡単にまとめておくと、九大工学部に受かるのに大事なことは以下です。
- 必要な情報を集める
- 九大工学部に受かる得点戦略を考える
- 学習計画を自分なりに作る
- 数学にこだわらない
- 理科が合格の生命線
- 復習は必須
- 目指すべきは合格者最低点+30〜40点
この辺りでしょうか?他にも大事なことはかなり話したので、この記事を何回も読んで九大工学部に必要な考え方を身につけてください。